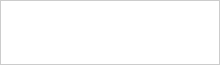2月12日、SMBC Group Digital Summit 2025が開催。東京大学 松尾豊教授は対談で、1週間前の講演に続く形でDeepSeekとAI技術の進化について語った。本対談では、金融業界の視点を交えつつ、AI技術の現状と未来について一層深い洞察が示された。
松尾氏は、前週のシンポジウム同様、DeepSeek報道の技術的な誤解を指摘し「過剰な反応」と一貫した見解を示しており、R1は強化学習によって思考プロセスを強化したモデルであり、GPU使用量の削減は実際にはV3モデルに起因するものであると改めて強調した。ファシリテーターがDeepSeekを大きな転換点と捉え、期待感を示すと、氏は必ずしもAI業界のゲームチェンジャーではないと述べ、強化学習の手法はオープンAIなどの他企業でも適用可能と解説。技術的実態や市場の過剰反応に対して慎重な姿勢を崩さなかった。この温度差がメディア報道の過熱感を浮き彫りにするともいえるだろう。
特に印象的だったのは、松尾氏が銀行の役割について、金融機関が単なるサービス提供者ではなく、企業のDXを推進する中心的存在になり得ると強調した点だ。取引データや資金の流れの中心に位置する銀行は、これらの情報を活用することで企業の成長戦略を支援できる可能性があると述べた。この視点は新鮮で、AIの社会実装のリーダーとして銀行の可能性を喚起する。SMBCの500億円規模の生成AI投資についても高く評価しつつ、グローバル基準ではようやく土俵に乗ったレベルと話し、投資規模だけでなく、技術理解と変革のスピードが重要であるとし、日本企業のAI投資と活用の遅れに対する課題意識を示した。
氏は、オープンソースモデルに追加学習を施すことで企業が独自のAIモデルを開発することが現実的な選択肢となってきた点に触れ、高精度なモデルを低コストで実現できる可能性があると解説。今回の対談を通じて松尾氏は、感情的な議論や過剰な期待に流されず、冷静な視点で技術と社会の関係を見極めることの重要性を改めて示した。特に金融業界において、AI技術を単なる効率化ツールとしてではなく、企業や社会全体の発展を支援する力として捉えることの重要性を示した。日本の金融業界と企業が、松尾氏の示した冷静でバランスの取れた視点を参考にしながら、持続的な成長に向けて積極的かつ継続的に行動することが期待される。